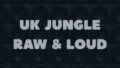70年代から80年代、ディスコは大衆的なダンスミュージックとして世に広まったが、一方でクラブシーンの中で独自に進化した音楽があった。
The Loft、Paradise Garage、The Music Box といった、今では伝説とされるクラブでプレイされ、メインストリームのディスコとは異なる路線を歩んだ音楽、それがアンダーグラウンド・ディスコだ。
アンダーグラウンド・ディスコとは?
派手なストリングスや煌びやかなプロダクションではなく、ダブ、エレクトロ、ラテン、ポストパンクなど異なる音楽要素を取り入れた自由なサウンドが特徴。
単に踊るための音楽ではなく、DJたちの実験場としても機能し、後のハウスやエディット・ミュージックへと繋がっていった。
そして近年、ハウスやテクノのルーツとして再評価が進み、リイシューや再発レコードも増え、当時は限られたクラブでしか聴けなかった楽曲もデジタル配信を通じて新たなリスナーに届くようになった。
70s~80s アンダーグラウンド・ディスコの名盤
メインストリームのディスコが華やかに輝いていた頃、クラブの片隅では別の形のディスコが育まれていた。DJたちがフロアの反応を見ながら、時に大胆に、時にじっくりと磨き上げた楽曲たち。
70s~80sのクラブシーンで愛されたディープなディスコアルバムを紹介!
Dinosaur L – 24→24 Music (1981)
Arthur Russell (アーサー・ラッセル) は、70年代から80年代のNYアンダーグラウンドシーンで活躍した、チェロ奏者、作曲家、プロデューサーで、ジャンルにとらわれない幅広い音楽を追求した人物。
彼はクラシックやミニマル・ミュージックを学びながら、ディスコの持つ”反復の美学”にも興味を持っていた。その探求の一つが、この Dinosaur L 名義のアルバム “24→24 Music”
この作品には、一般的なディスコにはない感覚がある。リズムは躍動しているのに、どこか緩く漂うような不思議なグルーヴ。ジャズの即興性、ダブの音響処理、ディスコのループ感が混ざり合い、常に変化し続ける。
この作品は、ディスコの枠にとどまらず、ハウスやエクスペリメンタル、エレクトロニカにも影響を与えた。Arthur Russell の音楽の中でも、特にダンスフロアに根ざした一枚。
“Go Bang”
Black Devil – Disco Club (1978)
Black Devil の “Disco Club” は、1978年にリリースされたにもかかわらず、異様なほどに未来的な響きを持っている。
このプロジェクトを手がけたのは、フランスの作曲家 Bernard Fèvre(ベルナール・フェーヴル)。彼は70年代にシンセサイザーを駆使した電子音楽を制作しており、この Disco Club でもアナログシンセを前面に押し出した異色のディスコを作り上げた。
Black Devil の音楽にはどこか冷たく機械的な感触がある。それがただの無機質なサウンドにならないのは、リズムやメロディが独特の浮遊感を持っているからだろう。
“Timing, Forget the Timing”
アルバムを象徴する一曲 “Timing, Forget the Timing”
機械仕掛けのように反復するリズムに、シンセの不穏なコードが重なり、どこか異世界の音楽のような雰囲気を作り出している。ヴォーカルもエフェクトがかかっていて人間味が希薄。
当時、このアルバムはほとんど話題にならなかったようだが、2000年代に入って再評価され、アポロ・レーベルから再発されたことでカルト的な人気を得た。70年代のディスコとしては異質なサウンドで、むしろエレクトロやシンセウェーブに近い感触がある。
Peech Boys – Life Is Something Special (1983)
Peech Boys の “Life Is Something Special” は、Paradise Garage のDJとして知られる Larry Levan(ラリー・レヴァン)がプロデュースを手がけた数少ないアルバムのひとつ。
ガラージのレジデント・ヴォーカリストであった Bernard Fowler(バーナード・ファウラー)を中心としたグループで、レヴァンのディスコへのアプローチをそのまま音楽として具現化したようなプロジェクト。
このアルバムの特徴は、ディスコとハウスの境界線が曖昧になりつつある時期の音を捉えていること。
まだハウスというジャンルが確立される前だが、トラックの作りやグルーヴには明らかにその兆候がある。リズムマシンの活用、深く響くリヴァーブ、シンセの持続音が作る空間的な広がり――どれも、後にシカゴやニューヨークのハウスミュージックへと引き継がれていく要素だ。
“Don’t Make Me Wait”
名曲 “Don’t Make Me Wait“ イントロから漂う独特の空気感、印象的なベースライン、反響するクラップ音。ヴォーカルはルーズでナチュラルな歌い回し。
印象的なのは、音の余白。従来のディスコのように詰め込まれたアレンジではなく、ビートとベース、ヴォーカルの間にゆとりがあり、グルーヴに深みを与えている。この感覚こそが、後のハウスミュージックに通じる重要な要素。
このアルバムは、ディスコの終焉とハウスの始まりをつなぐ、独特の立ち位置にある作品。ガラージ・クラシックとしても、ハウスの原型を探るうえでも、一聴の価値がある。
Wally Badarou – Echoes (1984)
Wally Badarou(ウォリー・バダルー)の名前は、ディスコファンよりもセッション・ミュージシャンの世界で知られているかもしれない。カリブ系フランス人の彼は、Level 42 のキーボーディストとして活動しながら、グレース・ジョーンズやミック・ジャガーの作品にも関わったマルチ・プレイヤーだった。そんな彼がソロとして生み出したのが、この “Echoes”
このアルバムの特徴は、ダンスミュージックでありながら派手な展開はほとんどなく、シンセの響きがじわじわと染み込んでくるような作りになっている。ビートは控えめな曲が多く、リズムの上に漂うようなメロディとサウンドのレイヤーが心地よい。
“Chief Inspector”
このアルバムの代表曲といえば、“Chief Inspector“
跳ねるベースと乾いたスネアが生み出すタイトなリズムに、シンセのリフが絡むシンプルな構成。その絶妙な引き算のバランスが、ファンクともディスコとも違う、不思議なテンションのダンスミュージックを生み出している。
この曲は、80年代のクラブシーンでもプレイされようたが、後のバレアリック・ビートやチルアウト・ミュージックの文脈でも語られることが多い。どこか都会的で洗練された雰囲気がありつつ、無駄を削ぎ落としたサウンドは今聴いても新鮮に響く。
ESG – You’re No Good (1981)
ESG(Emerald, Sapphire & Gold)は、ニューヨーク・ブロンクス出身の姉妹バンド。
ポストパンク、ファンク、ダブ、ディスコが混ざり合った、独特のミニマル・グルーヴを生み出したグループ。ディスコのビートにファンクのグルーヴ、そしてパンクの生々しさを乗せたサウンドは、当時のどのシーンにも完全には属さないものだったが、結果的に幅広い影響を残すことになった。
1981年にイギリスの Factory Records から7インチ盤としてリリースされたデビューシングル “You’re No Good” は、彼女たちの音楽性を強く印象づける3曲を収録、同年にアメリカの 99 Records からリリースされた EP “ESG” にも同じ3曲が収録された。
“Moody”
“Moody“は、ESG を象徴する一曲で、シンプルなベースラインと乾いたビートが繰り返され、ヴォーカルはシンプルながら妙にキャッチー。
同シングルに収録されている “UFO“ は後のハウスやヒップホップのプロデューサーたちにサンプリングされまくったことでも知られている。Public Enemy や The Notorious B.I.G、J Dilla といったアーティストたちが彼女たちの楽曲をネタに使い、その影響はヒップホップやエレクトロの領域にも及んだ。
Liquid Liquid – Liquid Liquid (1983)
Liquid Liquid は、1980年代初頭のニューヨークで誕生したバンド。
ポストパンク経由の異端ディスコグルーヴを生み出し、ミニマルなベースラインとタイトなパーカッションを武器に、ディスコ、ファンク、ダブ、ラテンを独自に再構築した。彼らの音楽は、当時のNYのクラブシーンと密接に結びつき、アンダーグラウンド・ディスコの流れの中で異彩を放った。
バンドと同名のアルバム “Liquid Liquid“ (1983) は、彼らの持つダンスグルーヴが純粋な形で刻み込まれた作品。ファンクの跳ねるビートとミニマルな反復が、ストイックながらも強烈な高揚感を生み出している。
“Cavern”
このアルバムの中で象徴的なのが “Cavern”
うねるベースとドライなドラムが生み出すグルーヴは、シンプルながらも中毒性が高く、無駄を削ぎ落としたダンスミュージックの極致ともいえる。
このベースラインは後に Grandmaster Melle Mel の “White Lines“ にサンプリングされ、ヒップホップ史にもその名が刻まれた。
Liquid Liquid のサウンドは、メインストリームのディスコとは一線を画し、アンダーグラウンド・ディスコの持つグルーヴの本質を別の角度から引き出した。唯一無二の存在。
Candido – Dancin’ and Prancin’ (1979)
ディスコといえば4つ打ちのビートと煌びやかなストリングスを思い浮かべるかもしれないが、そこに生々しいラテン・パーカッションが加わるとどうなるか?Candido の “Dancin’ and Prancin’ “は、そんな問いに答えたアルバム。
カンディド・カマロ は、キューバ出身のコンガ奏者。ジャズ畑で長く活動していたが、70年代後半のディスコブームの流れに乗り、自身のパーカッションを前面に押し出したディスコ作品を制作した。それがこのアルバム。
コンガ、ボンゴといったラテン・パーカッションが、ディスコの4つ打ちと絡み合い、独特の熱量を持ったグルーヴを生み出している。
“Jingo”
アルバムのハイライトは、やはり “Jingo“
トニー・アレンの影響を受けたようなリズムワークに、アフロ・ラテンのエッセンスがふんだんに盛り込まれている。力強いコンガの連打、シンプルながらも中毒性のあるヴォーカル、そして徐々に高揚していく展開。
Jingo はパラダイス・ガラージやロフトのセットリストにもよく登場し、DJたちに愛されたクラシックのひとつだった。ラテン音楽とディスコのクロスオーバーが生み出した、極上のグルーヴを体感できる一曲!
The Chaplin Band – Dancing’ On Town Square (1982)
ディスコの黄金期には、アメリカだけでなくヨーロッパからも数多くのディスコ・アクトが登場した。その中でも、The Chaplin Band は特異な存在。
オランダ出身の彼らは、イタリア産ディスコ(イタロ・ディスコ)とニューヨークのクラブサウンドの中間にあるような、独特のスタイルでアルバム “Dancing’ On Town Square” を作り上げた。
当時のイタロ・ディスコは、シンセを多用したキャッチーなメロディと華やかなアレンジが特徴。一方、ニューヨークのクラブシーンでは、よりファンク寄りでグルーヴを重視したディスコが流行していた。The Chaplin Band はその両方の要素を取り入れ、メロディの美しさとダンサブルなグルーヴを融合させた。
“Il Veliero”
このアルバムの象徴的なトラックが “Il Veliero“
シンセのリフとゆったりとしたビートが印象的で、徐々に高揚感を生んでいく。シンプルなベースラインと反復するメロディが、じわじわとフロアの熱を高めるディスコ・トラックで、パラダイス・ガラージやロフトのDJたちにも好まれたようだ。
派手なディスコ・ヒットではないが、フロアの空気を一変させる力がある。クラシックなディスコともイタロ・ディスコとも少し違う、独自のグルーヴが楽しめる一枚。
アンダーグラウンド・ディスコが生み出したムーブメント
アンダーグラウンド・ディスコは単なるダンスミュージックではなく、クラブシーンの中で独自に進化し、次の時代の音楽に大きな影響を与えた。
メインストリームのディスコが商業化していく中で、クラブの現場でより自由で実験的なアプローチを求めるDJたちによって育てられた音楽だ。
重要な役割を果たしたのが、The Loft、Paradise Garage、The Music Box といったクラブだ。
The Loft – David Mancuso
The Loft の創始者 David Mancuso (デヴィッド・マンキューソ) は、一般的なDJとは異なり、レコードをミックスせず、1曲ずつ丁寧に流すスタイルを貫いた。
彼が求めたのは、音楽が持つ純粋な高揚感を最大限に引き出すこと。ロフトでは商業的なヒット曲よりも、より深いグルーヴを持つ楽曲が好まれ、ディスコの可能性が広げられていった。
Paradise Garage – Larry Levan
Paradise Garage の DJ Larry Levan (ラリー・レヴァン) は、エフェクトやミキサーを駆使し、ディスコを単なる「曲」ではなく、ダンスフロア全体の体験として構築していった。
彼のプレイは曲の構造を変え、リズムを再構築することで、新たな音楽の流れを生み出す。レヴァンが支持した楽曲は、ディスコとハウスの中間的なサウンドを持ち、Peech Boys の “Don’t Make Me Wait” のように、ディスコの次なる形を示唆するものも多かった。
The Music Box – Ron Hardy
シカゴの The Music Box は、ディスコとハウスをつなぐ場所だった。
Ron Hardy(ロン・ハーディ)は、既存のディスコ・トラックを大胆にエディットし、よりハードでリズミックな方向へと進化させた。ハーディのプレイは、シカゴ・ハウスの誕生に直結し、ディスコのグルーヴを次の世代へと引き継いだ。
再評価されるアンダーグラウンド・ディスコ
70年代~80年代にかけて、商業的なディスコが洗練されていく一方で、クラブで流れるディスコはより実験的で、ジャンルを越えたサウンドへと進化した。
かつては限られたクラブでしか聴けなかったが、レコードの再発やDJの発掘により、今では新世代のリスナーにも広がっている。入手困難だったレコードも、再発やコンピの充実で身近になり、DJの新しい解釈によってシーンは進化を続けている。
また、以前は限られた場でしか聴けなかった楽曲も、ストリーミングやYouTubeなどで手軽にアクセス可能になり、新たなリスナー層がディスコの深みを探求している。
アンダーグラウンド・ディスコは過去の遺産ではなく、実験精神を保ちながら今も進化し続けるサウンドとして、ダンスフロアを揺らし続けている。